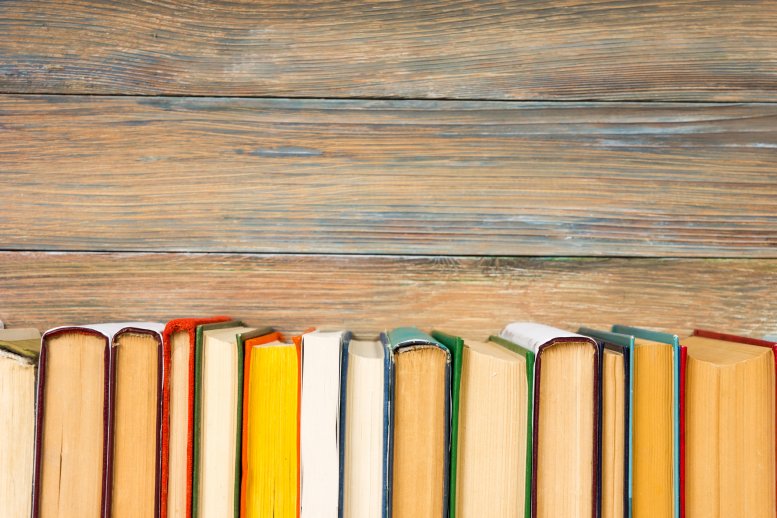
「それでも、日本人は「戦争」を選んだ」読みました。本書は日清戦争から太平洋戦争までの講義を五日間にわたって学生の方たちと歩んでいく内容です。
各戦争の中で単に「過去にこういう戦争があった」というだけでなく、なぜ、その戦争が起きたのか、各国がどういう思惑で行動し、日本も戦争という道を選ばざるを得なかったのか、ということが詳細にお話されていて、知らないことばかりでした。戦争時代の背景を感じることができる、大切な一冊だと思います。
特に印象深かったのは、中国の「胡適」という方で、太平洋戦争が起こる前から、米英を戦争に巻き込むために日本に対してどういう戦略を取ればいいか、その先見の明というか予測がそのまま未来に現実になっていく所は少し怖いぐらいです。(たぶん、相当に優秀な方だったのか、と思わざるを得ないほど)
1900年初頭は情報も行き届いていない時代だし、国(政府)の都合の良い方向に国民も進まざるを得ない、という現実もあったと思います。
普通選挙もまだ平等になかった時代。でも、それも約100年ぐらいの歴史からするとごく最近の出来事なんですよね...
昔は軍が日本の政治に関わっているというのもあると思いますが、帝国主義の世界では、日本も主権を他の国に脅かされないよう、一生懸命に命を賭けて守ってもらい、数知れぬ犠牲の中、今の日本につながっていくわけです。
少なくても、現在を生きる今の我々ができることは、昔にあった戦争の背景や、出来事を知ること、そして、それらを噛みしめて、日々の感謝を忘れず、また、今後にどう生かしていくのかを各個人が考え、行動することが大事だと思います。
個人個人がそうした自覚が必要だと思うし、その先にこの社会の中で、自分なりの貢献をしていくことが、「平和」というものが持続可能性なものになるのではないか、と思います。
本書は講義の途中で、加藤陽子先生が紹介してくれている書籍が多数あるので、今後もそれらの本を読んで、勉強を進めていきたいと思います。
35: なにが日本国憲法をつくったか
日本国憲法といえば、GHQがつくったものだ、押し付け憲法だとの議論がすぐに出てきますが、そういうことはむしろ本筋ではない。ここで見ておくべき構造は、リンカーンのゲティスバーグでの演説と同じです。巨大な数の人が死んだ後には、国家には新たな社会契約、すなわち広い意味での憲法が必要になるという真理です。
41: 戦争相手国の憲法を変える
戦争は国家と国家の関係において、主権や社会契約に対する攻撃、つまり、敵対する国家の憲法に対する攻撃、というかたちをとるのだと。
64: 過去の歴史が現在に影響を与えた例とは
ロシア革命を担った人たちが、フランス革命の帰結、ナポレオンの登場ということを知ったうえで、スターリンを選んだというのは、かなり大きな連鎖であり、教訓を活かそうとした結果の選択です。一つの事件は全く関係のないように見える他の事件に影響を与え、教訓をもたらすものなのです。しかし、ここが大切なところですが、これが人類のためになる教訓、あるいは正しい選択であるとは限らない。スターリンは1930年代後半から、赤軍の関係者や農業の指導者など、集団化に反対する人々を粛清したことで悪名高い人ですね。犠牲者は数百万ともいわれる。
68: 過去の歴史が現在に影響を与えた例とは
レーニンの後継者がスターリンにされたことで人類の歴史が結果的にこうむってしまった厄災を話ましたが、この西郷の一見を統帥権独立の関係も、人類の歴史が結果的にこうむってしまった厄災の一つといえるかもしれませんね。
日中戦争、太平洋戦争のそれぞれの局面で、外交・政治と軍事が緊密な連撃をとれなかったことで、戦争はとどまることを知らず、自国民にも他国民にも多大な惨禍を与えることになったからです。
79: 戦争をとめられなくなった理由
人類は本当にさまざまなことを考え考えしながらも、大きな厄災を避けられずにきたのだということを感じます。私たちには、いつもすべての情報が与えられるわけではありません。けれども、与えられた情報のなかで、必死に、過去の事例を広い範囲で思いだし、最も適切な事例を探しだし、歴史を選択した用いることができるようにしたいと切に思うのです。歴史を学ぶこと、考えてゆくことは、私たちがこれからどのように生きて、なにを選択してゆくのか、その最も大きな力となるのではないでしょうか。
138: 普選運動が起こる理由
戦争には勝ったはずなのに、ロシア、ドイツ、フランスが文句をつけたからといって中国に遼東半島を返さなければならなくなった。これは戦争に強くても、外交が弱かったせいだ。政府が弱腰なために、国民が血を流して得たものを勝手に返してしまった。政府がそういう勝手なことをできてしまうのは、国民に選挙権が十分にないからだ。との考えを抱いたというわけです。
155: シュタインの予言が現実に
シュタインが山形に言ったこと、「シベリア鉄道(中東鉄道として敷設されます)それ自体は怖くない。中国の土地を通過しなければならないから、それがロシアにとって制約要因となる」という条件が、まずは飛んでしまったということですね。さらに、中国がロシアと手を組んで、中国とロシアの合弁会社によって中東鉄道とその南支線が敷設されてしまえば、制約要因もなくなり、しかも、朝鮮半島の東ではないけれでも、遼東半島の南に凍らない港を持つことができてしまう、つまり、極東の海に海軍を興すことができてしまう。鉄道敷設に関して、中国とロシアの間で1896年と98年の二度にわたって結ばれた条約は、日本にとって悪夢を見ているようなものだったに違いありません。
157: ロシアの対満州政策と中国の変化
1902年に満州から撤兵しますよといったのに、ロシアを撤兵しない。中国と約束したはずの撤兵期限をなかなか守らないという事態を見て、イギリスは日本に同盟を提案するのです。こうして1902年1月、日英同盟協約が調印されます。
178: 戦場における中国の協力
最も重要だったのは戦場における中国側の協力です。このときの戦場は満州でした。略
ここでの諜報作戦は、日本軍が圧倒的に勝ちました。それは中国の中立とはいえ日本を援助する地域の官僚たちのバックアップがあったからです。土地勘のある農民たちが日本軍の諜報のために働いてくれた。
↓なぜ、協力してくれた?
清国(中国)は、「ロシアがお金をくれたのはうれしい。けれどロシアについたままだとどうも国をとられてしまうんじゃないか」と思うようになる。だったら、ロシアより弱い日本と協調して満州を門戸開放してもらったほうがよい、開放までならいいじゃないか、と日本に近づく。
186: 戦争はなにを変えたのか
日露戦後、増税がなされたことで、選挙資格を制限する直接国税10円を結果的に払う層が二倍に増える、つまり選挙権を持つ人が二倍に増えたこと、これが大切なポイントです。
188: 世界が総力戦に直面して
この戦争(第一次世界大戦)でなにが変わったかという点について、世界の場合と日本の場合とで分けて考えてみましょう。
まず、世界という点では、ヨーロッパで長い伝統を持っていた三つの王朝が崩壊してしまった。これが最も大きな変化といえます。一つ目がロシア。連合国の一員であったロシアでは、長引く戦争の混乱から国内に革命が起きてロマノフ朝が崩壊します。ここにいう革命とは(略)ロシア革命のことです。
二つ目がドイツ。同盟国側の中心であったドイツでは、国内で労働者による武装蜂起が起き、皇帝だったヴィルヘルム二世が逃亡した結果、ホーエンツォレルン朝が崩壊します。三つ目がオーストリア。ドイツと同じく同盟国であったオーストリアも敗戦によってハプスブルク帝国がなくなります。戦争の影響の二つ目は、帝国主義の時代にはあたりまえだった植民地というものに対して批判的な考え方が生まれたことです。植民地獲得競争が大戦の原因の一つとなったとの深い反省からです。帝国主義とは、ある国家や人民が、他の国家や人民に対して支配を拡大しようとする努力一般を指しますが、これまで国家の名前で堂々となされてきた植民地獲得や保護国化が、そのままでは世界から承認されないようになったのです。
221: イギリスが怖れたこと
1925年になにが起こっているかというと、中国共産党が上海で組織した反英ストライキが起きていますね。イギリスへのボイコットに中国は動く。ストライキの矢面に立たされることなどは、非常に困る。イギリスは、とにかく、貿易面で打撃をこうむりたくないので、参戦しようとする日本に対し、あまり南まで活動しないでね、とかなりしつこくお願いするのです。
229: 松岡洋右の手紙
日本が批判をあびたのは山東問題のことです。略
中国に返還するためにといってドイツから奪ったのに、結局、日本は自分のものにしてしまったとの、世界および中国からの非難が激しかったことがわかります。
手紙文からは松岡の苦悩が伝わってくるようです。自分は頑張ってプロパガンダをした。けれど、他の人だった強盗を働いているのだからう自分が咎められる筋合いはないという弁明は、「人をして首肯せしめる疑問」、つまり本当に人を納得させることはできないといっている。
239: 若き日のケインズ
当時、大恐慌を脱するためには、政府の公共投資などを少なくして、経済界の自由にまかせるべきだ、との処方箋が広く支持を集めていました。このときケインズは、いや、そのような考え方はまちがっていると大胆に述べたのです。大恐慌を脱するためには、政府はどんなに赤字を出してもいいから政府の財政機能を通じた公共投資を積極的に行い、とにかく失業者がゼロになるまで需要を拡大しないさい、と論じます。
242: 若き日のケインズ
1919年の時点で、「ケインズの言うとおりに、寛容な賠償額をドイツに課していれば、あるいは29年の世界恐慌はなかったのではないか、このように予想したい誘惑にかられてしまいます。そうであれば、第二次世界大戦んも起こらなかったかもしれません。けれども、ケインズの案は通らなかった。その結果ケインズは「あなたたちアメリカ人は折れた葦です」という手紙を残してパリを去ることになりました。
262: 満州事変と東大生の感覚
憲兵は司法大臣の指揮も受け、治安警察法や治安維持法など国民の思想を取り締まる権限も持っていたということです。この憲兵という存在が、昭和期の言論をより狭くしていくのです。
戦時下の狂信的な面が語られるとき、憲兵の存在とともに語られることが多いです。
266: 満蒙は我が国の生命線
ある国の国民が、ある相手国に対して、「あの国は我々の国に対して、我々の生存を脅かすことをしている」あるいは、「あの国は我々の国に対して、我々の過去の歴史を不定するようなことをしている」といった認識を強く抱くようになっていた場合、戦争が起こる傾向がある
291: 独断専行と閣議の追認
今の世のなかは、特定の思想信条を持っているからといって、国家や国家機関によって危害を加えられたり拘束されたりすることは、まず、ないといっていいでしょう。現在「その筋」といえば、暴力団のことを指しますが、当時は、軍、そのなかでも海軍ではなく陸軍と警察を指すのが一般的でした。つまり、戦前においては、「その筋」の人々がなにをやらかすかわからない、怖い存在であると思われていた。
300: 吉野作造の嘆き
戦争に反対する勢力が治安維持法違反ということですべて監獄に入れられてしまっていた
301: 帝国議会での強硬
1932年10月の時点で、日本社会のなかに、どれほど苦しくとも不正はするまいといった古き良き時代の常識や余裕がなくなっていて、しかも日本側には、日露戦争に際して日本が世界に向かって正々堂々と主張できたような、戦争を説明するための正当性がどうも欠けている、そのような状態になったということです。
312: すべて連盟国の敵!!
強硬に見せておいて相手が妥協するのを待って、脱退せずにうまくやろうとしていた内田外相だったわけですが、熱河侵攻計画という、最初はたいした影響はないと考えられていた作戦が、実のところ、連盟からは、新しい戦争を起こした国と認定されてしまう危険をはらんでいた作戦であったことが、衝撃的に明らかにされてゆく。天皇も首相も苦しみますが、除名や経済制裁を受けるよりは、先に自ら連盟を脱退してしまえ、このような考えの連鎖で日本の態度は決定されたのです。
329: 汪兆銘の選択
日本軍によって中国は1938年10月ぐらいまでに武漢を陥落させられ、重慶を爆撃され、海岸線を封鎖されていました。普通、こうなればほとんどの国は手を上げるはずです。常識的には降伏する状態なのです。しかし、中国は戦争を止めようとはいいません。胡適などの深い決意、そして汪兆銘のもう一つの深い決意、こうした思想が国を支えたのだと思います。
341: 天皇の疑念
開戦の決意をせず戦争しないまま、いたずらに豊臣氏のように徳川氏に滅ぼされて崩壊するのか、あるいは、七割から八割は勝利の可能性のある、緒戦の大勝に賭けるかの二者択一であれば、これは開戦に賭けるほうがよい、との決断です。このような歴史的な話をされると、天皇もついぐらりとする。アメリカとしている外交交渉で日本は騙されているのではないかと不安になって、軍の判断にだんだんと近づいてゆく。
342: 天皇の疑念
(昭和41年)当時日本は、イギリス、アメリカ、オランダ、中国、これらの国々が悪いのは自由主義を信奉する資本主義国だからで、有産階級や資本家が労働者や農民を搾取している悪い国だと、さかんに国民に説明していた。その点でいえば、ソ連は社会主義国であって資本主義国とは違う。とくに経済政策の点では国家による計画経済体制をとっているのだから、反自由主義、反資本主義ということで、日本やドイツと一致点があるのだ、こう日本側は考えようとしていたのだと思います。
358: チャーチルのぼやき
ドイツ流の、一国一党のナチス党による全体主義的な国家支配に対する憧れが日本にも生まれてくる。衆議院では相変わらず政友会や民政党などに既成政党が多数を占め、貴族院では生まれた家柄がよいだけの無能な貴族が多数を占めている、これではダメだというのです。
403: あの戦争をどう見るか
天皇を含めて当時の内閣や軍の指導者を送りだそうと動くような県の役人、あるいは村長、あるいは村人の側にまわっていたのではないかと想像してみる姿勢、この二つの姿勢をともに持ち続けること、これがいちばん大切なことだと思います。
