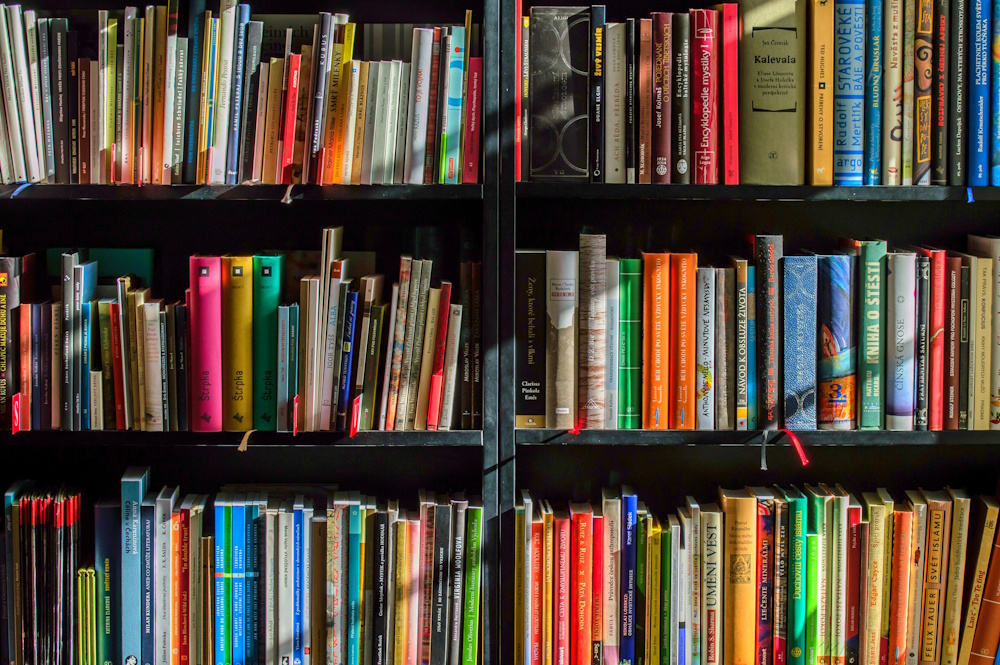
「安倍晋三回顧録」読みました。本書を読んで率直に思ったこと(というか以前からもだけど)。安倍さんに可能ならば、もう一度総理大臣をやってもらいたい。(というか、それでも歴代最長やっていただいて本当に良かった。まあ、もし存命でもそれはかなわないことか..)
昨今、財務省解体の声が大きくなってきてますが、本書を読んでいても、財務省はとりあえず「クソ」というのは、普通に理解できると思います。それがわかるだけでも本書を読む価値があるのかなと。
安倍さんがいなくなってから、岸田政権になって、財務省のやりたい放題が始まり、ステルス増税含め、増税増税が繰り返されてきたことは日本国民ならば誰でもご存じだと思います。(物価高も実は増税ですよ?)
安倍さんは財務省の打ち出す「財政健全化」イズムに第一次政権はそれなりに寄り添っているのですが、経済の勉強会を開いていく上で第二次政権の時には財務省のいう、「財政健全化」は政策として間違っていること(デフレ時に増税をするという、さらに経済を凍らせるような政策はあきらかに間違っている)ということに気づきます。
しかし、消費増税を二回も延期をし、最終的には増税をせざるを得ない所は、やっぱりそれぞれのメンツ(麻生さんとかね..)を潰さないように立ち回っていたのだと思います。(結果、安倍政権で二度の消費増税を達成したのだから、結局財務省の思惑通りになっているという現実はあるし、多分とんでもない権力闘争があるんだと思う)
あと、トランプとの親密な関係や、プーチンとの外交は目を見張るものがあることが理解できます。安倍さんがもしご存命だったとしたら、トランプ関税がそもそも発動されていたかどうかもわからない(多分、安倍さんにアドバイスをトランプは求めて、多分、安倍さんがそれを正しく導いてくれてそう)な気がしてます。それぐらい、トランプは安倍さんのことを慕っていたし、国を率いるリーダーの先輩として信頼していた。
なんか、安倍さんがこの世にいなくなってから、日本は一気に悪い方向に進んでいるような気がします。
みんな、危機感あるのかな?参院選、ちゃんと考えて、増税路線の党、実は増税路線の党、国民の声を代弁してくれそう?な党、日本を再生へと導いてくれそう?な党(そのままか汗)
投票しなければ、いつまでたっても、財務省のやりたい放題で、「なんで、いつまでも生活が苦しいの?」という無知な悩みが病気のようにまとわりつく未来がやってくると思います(そんな未来はやだな..)
結局は官僚をやりたい放題にさせているのも、蓋を開けてみると、国民なんですよね。
日本の投票率の低さは折り紙付き。ちゃんと政治に関心を持って、全国民が選挙に参加したいものです。
94: 日銀と財務省の誤りを確信する
デフレ脱却の勉強会の会長を頼まれて、勉強会を発足させました。そうした中で、日銀の金融政策や財務省の増税路線が間違っていると確信していく。そこでアベノミクスの骨格が固まってくる。こうやって安倍政権は、産業政策のみならず金融を含めたマクロ経済政策を網羅することになるのです。極めて珍しい内閣だったと思います。
100: 総裁再登板へ
第一次内閣を振り返って思うのは、運は、自分で手放してしまうこともある。手放したものを握り返そうとしても、砂を握るみたいに、手の中でぼろぼろ落ちていくのです。潮目は、一瞬で変わる。
そうならないように、常に最善を尽くすことが大事なのです。
111: アベノミクス始動
07年に首相を退陣し、12年までの5年の間に、リーマンショックがあり、東日本大震災が起きた。雇用情勢も悪く、有効求人倍率は0.6程度に落ち込んでいた。デフレもずっと続いているわけです。なぜ物価が継続的に下がって社会全体の経済活動が縮小していくのか。もちろんデフレには、賃金低下やイノベーションの問題など複合的な要因はありますが、基本的には貨幣現象の問題です。社会に出回る貨幣が多いとインフレになり、少なければデフレになります。そう考えれば、長年の金融政策が間違っていたのは明らかでしょう。
私が官房長官時代、小泉純一郎首相と一緒に福田俊彦日銀総裁に量的緩和の解除は時期尚早だから辞めてくれ、とお願いしたにもかかわらず、06年に解除してしまったこともありました。
112: アベノミクス始動
世界中どこの国も、中央銀行と政府は政策目標を一致させています。政策目標を一致させて、実体経済に働きかけないと意味がない。実体経済とは何か。最も重要なのは雇用です。2%の物価上昇率の目標は、インフレターゲットと呼ばれましたが、最大の目的は雇用の改善です。
114: アベノミクス始動
私が野党の総裁として金融緩和を掲げ、マスコミや経済学者からさんざん批判されていた時に、黒田さんは私の政策を評価していたのです。国際機関とはいえ、政府側の立場の銀行総裁が当時、野党だった党首の政策を、ですよ。その度胸があれば、そして私と政策が一致できれば、と考えました。しかも、財務省出身ではないですか。だから、財務省も受け入れざるを得ないと思いました。
116: 内閣法制局長官交代、集団的自衛権の憲法解釈変更へ
第一次内閣の時も、法制局は私の考えと全く違うことを言う。従前の憲法解釈を一切変える気がないのです。槍が降ろうが、国が侵略されて一万人が亡くなろうが、私たちは関係ありません、という机上の理論なのです。でも、政府には国民の生命と財産に対して責任がある。法制局は、そういう責任を全く分かっていなかった。
128: 国益重視の国家安全保障会議(NSC)
景気が厳しいとは言っても、企業には内部留保があるわけです。流動性のある現預金は少ないという主張もありましたが、余剰資金があるのは事実です。社会に染みこんでしまったデフレマインドを払拭するためには、給料を上げることが大きな力になると思ったのです。当然、雇用状況の改善が優先なのですが、それと同時に賃金が上がっていくという環境をつくりたかった。政府が賃上げを手動するなんて、通常ないことだし、社会主義的に見えるかもしれませんが、ここはお願いしようと判断しました。
128: 国益重視の国家安全保障会議(NSC)
まずは賃金を上げろ、という民主党的なアプローチではクビ切りが起きかねない。だから、企業の経営環境の改善を最優先に行ったのです。1ドル80円前後という民主党政権時代の行き過ぎた円高は、安倍政権で100円超になっていたわけです。企業はその後、最高の収益を上げていく。でも、賃金がなかなか上がっていかない。だから賃上げを要望し続けたんです。
138: 官邸一強の象徴?内閣人事局発足
政治主導とは何か。根本は選挙で政策を公約し、国民から多数の支持をいただいて政権を取り、約束したことを実行していくことでしょう。選挙で勝つためには、公約を実現することが大事なんです。
内閣が政策を実行しようとしているのに、官僚が自分たちの役所の利益にならないからと、妨害するのは許されません。→石破は公約は守られるわけではない、という..と全然ちがう..
141: 日朝交渉 期待外れのストックホルム合意
金正日は、拉致を認めた02年9月17日午後の会談で、文書を読むのですけど、読みながら、小泉さんを上目遣いでちらちらと見てくるのです。どういう反応をするかと、とにかく米国が怖かったんですよ。
だから日本に近づいてきたのです。そう考えると、米国が脅威にならないと、拉致問題も進展しないと言える。
142: 日朝交渉 期待外れのストックホルム合意
小泉訪朝が終わり、平壌から帰国する政府専用機内では、北朝鮮への援助内容をどうしようか、という議論が始まったのです。私は「横田めぐみさんを含め、8人も亡くなっているという話が出ているのに、援助なんてできるはずがないだろ」と猛反対したのです。結局、援助は時期尚早となりましたが、外務省に任せていたら、どうなっていたことか分かりません。
147: 増税延期を掲げた「奇襲」の衆院解散
自民党の幹事長は、党の資金配分を一手に担っています。党の躍進のためにお金を使うのであれば良いのですが、仮に自分の派閥を大きくするとか、自分の総裁選の準備のためにお金を使っていたとしたら、それは看過できない。菅さんは党内に目を光らせていて、「石破さんの幹事長続投は政権の不安定要因になる」と言っていました。
148: 増税延期を掲げた「奇襲」の衆院解散
増税を延期するためにはどうすればいいか、悩んだのです。デフレをまだ脱却できていないのに、消費税を上げたら一気に景気が冷え込んでしまう。だから何とか増税を回避したかった。しかし、予算編成を担う財務省の力は強力です。彼らは、自分たちの意向に従わない政権を平気で倒しに来ますから。財務省は外局に、国会議員の脱税などを強制調査することができる国税庁という組織を持っている。
162: キーワードを網羅した戦後70年談話
村山(富市)談話は、日本だけが植民地支配をしたかのごとく書かれている。戦前は欧米各国も植民地支配をしていたでしょう。人種差別が当たり前の時代、アフリカで残虐なことをしていた国もある。ベルギーの国王が残虐行為をしたとしてコンゴ共和国に謝罪したのは、2020年ですよ。日本は過去、繰り返し中国や韓国、東南アジアに謝罪し、政府開発援助(ODA)などを通して実質的に賠償までしてきたでしょう。
162: キーワードを網羅した戦後70年談話
19年のフランス・ビアリッツでのG7サミットで、ロシアによるクリミア半島の併合問題を議論している時、ある首脳が「クリミアを侵略したという一点をもって、ロシアを非難しなければならない」と言ったのです。これにボリス・ジョンソン英首相は反対しました。ジョンソンは「侵略という言葉を軽々に使わないでほしい。英国は歴史上、今の世界の4分の1の国を侵略したんだ」と言ってました。歴史学者のジョンソンはさすがですよ。
179: 1時間半もの長電話 米国トランプ大統領との会話
通商や貿易の世界で、自国第一主義を主張するのはまだ許せるのですが、安全保障政策で米国が自国の利益ばかりを考え、国際社会のリーダーの立場を下りてしまったら、世界は紛争だらけになってしまいます。私は「国際社会の安全は米国の存在で保たれている」とトランプには繰り返し言いました。米国の国家安全保障会議(NSC)の面々と私は同じ考えだったので、NSCの事務方は、私を利用して、トランプの考え方を何とか改めさせようとすらしました。
186: 自信を深めていった中国の習近平国家主席
私の任期中、習近平はだんだんと自信を深めていったと思います。10年に世界第二位の経済大国となって以降、より強硬姿勢となり、南シナ海と軍事拠点化し、香港市民から自由も奪った。そして次は台湾を狙っている。毛沢東が経済失政で飢餓を引き起こした反省から、中国は鄧小平時代に集団指導体制が敷かれましたが、今、習氏は異論を封じている。非常に危険な体制となっているわけです。
197: EU首脳の前で俳句を詠むことに..
私はEUの面々にも、中国の問題点を説明していました。ファン=ロンパイは14年のブリュッセルの会談で、「安倍さんの警告が、だんだんわかってきた」と言い出した。何事かと思ったら、「先般、中国の習近平国家主席がEUを訪問する時、米国大統領と全く同じように接遇しろ、と中国側がしつこく求めてきた。とても辟易した」と言うわけです。私は「中国は、大国として振る舞いたいのでしょう。その傾向はますます強くなりますよ」と答えました。
224: 増税先送りへ
全体として大きな仕掛けをつくったわけですね。増税先送りへの財務省の抵抗は強かった。でも、デフレ状態の時に消費増税を2回も短期間で行うという考え方が間違っているのです。しかも、増税した分の五分の四は、借金の返済に充てるという、実体経済を全く無視した政策なのです。予定通りに消費税を引き上げていたら、経済は大変なことになっていましたよ。だから、19年の増税時には、増収分の使途を変更し、全世代型社会保障という形にして幼児教育や保育の無償化に充てたのです。
236: 米大統領選でトランプ氏当選
(トランプ会談)
中国が26年間で国防費を約40倍に増強した点を、データを使いながら説明しました。中国軍に潜水艦の数は、米国に匹敵しようとしている。なぜこれほど増強したのか。歴史問題を抱えている日本に対抗するためではない。海上自衛隊の潜水艦がターゲットではないんだ、と。米国にチャレンジしようとしている。太平洋に展開する米海軍の第七艦隊を狙っているのだ、という話をしました。
だからこそ、日米同盟が重要だと。在日米軍は日本の防衛だけでなく、アジア太平洋からインド洋まで広大な海域の安定に貢献し、米国が優位な立場を保つ役割を担っている。それが米国の経済的な利益にもつながっている。と強調しました。米国外で唯一、米海軍の空母を整備できる場所は、横須賀基地だけだという点も指摘しました。
二点目は経済関係です。貿易赤字を均衡させることばかりに注目すべきではない、日本が他国に比べていかに米国内で投資をし、雇用をつくっているかという説明をしました。トランプは反論せず、淡々と聞いていましたよ。
284: 厚労者の資料改竄
労働法制の議論をしていて感じたのは、固定観念にとらわれている人が多かったことです。労働組合は、年功序列や新卒の一括採用を前提に、旧来の労働者の待遇を良くすることに熱心でした。働き方改革という言葉が定着し、世の中の「長時間労働イコール善」という考え方はだいぶなくなったでしょう。ブラック企業は、敬遠されるようになりました。苦労してやった甲斐はありました。
288: 森友問題再燃、財務省による決裁文書の改竄
財務官僚は、鑑定の首相執務室に複数で来て、私に財政政策について説明をする時、一人の役人しかしゃべらないのです。同席している財務省の数人は、私が何を言うかメモを取っているだけなのです。
私が「うーん」と考えていても、誰も発言しません。私の前では一切議論しない。要は、情報収集が目的で官邸に足を運んでいるのです。そして官邸を去ってから、財務省内で作戦会議を開いて対応を決める。
私が増税に慎重な話をした場合、私の方針を覆すために、いろいろと画策するわけです。
312: 安倍政権を倒そうとした財務省との暗闘
小泉内閣も財務省主導の政権でした。消費税は増税しないと公約しましたが、代わりに歳出カットを大幅に進めることにしたわけです。私も第一次内閣の時は、財務官僚の言うことを結構尊重していました。でも、第二次内閣になって、彼らの言う通りにやる必要はないと考えるようになりました。だって、デフレ下における増税は、政策として間違っている。ことさら財務省を悪玉にするつもりはないけれど、彼らは、増収の増減を気にしているだけで、実体経済を考えていません。
313: 安倍政権を倒そうとした財務省との暗闘
私は密かに疑っているのですが、森友学園の国有地売却問題は、私の足を掬うための財務省の策略の可能性がゼロではない。財務省は当初から森友側との土地取引が深刻な問題だと分かっていたはずなのです。でも、私の元には、土地取引の交渉記録など資料は届けられませんでした。森友問題は、マスコミの報道で初めて知ることが多かったのです。
321: 7年ぶりの訪中、中国との付き合い方
第二次内閣以降の7年9か月間で、私は81回、海外出張に出かけました。私は世界中のどの国の首相と会談しても、必ず中国の話題を出して、軍備増強や強引な海洋進出を警戒すべきだと説いてきました。すると、私の考えに同調する首脳もいれば、そうでない首脳もいる。中国と親しい国であれば、私が中国の悪口を言っていることを告げ口するでしょう。それは百も承知で、あえて言うのです。
なぜかというと、これは勘でしかありませんが、中国という国は、こちえらが勝負を仕掛けると、こちらの力を一定程度認めるようなところがあるのではないか、と。そして警戒し、対抗策を取ってくる。
324: 7年ぶりの訪中、中国との付き合い方
賄賂がほしい人に、道徳を説いても仕方がないでしょう。ならば、どうするか。開放性や透明性の確保、債務の健全性など、こちらが原則を出して、その基準を守るならば、日本も中国の協力をしようと転換したのです。外交の基本はリアリズムです。イデオロギーに基づく外交をやっても、誰も付いてきてくれません。世界の国々は、いかに国益を確保するかを巡ってつばぜり合いをしているわけでしょう。
硬直的な考え方にとらわれていたら、結局、国は衰退しちゃいます。
